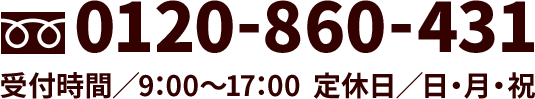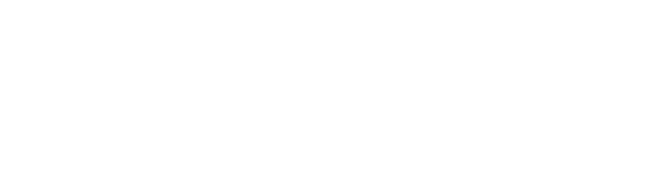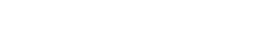住宅の豆知識
2021年 台風に備えた雨漏り対策リフォーム
- 住宅の豆知識

2019年10月に発生した令和元年東日本台風 (台風19号) により、埼玉県内では これまでにない記録的な大雨・強風、河川の氾濫による人的・住家被害ならびに浸水・土砂災害、停電、鉄道の運休などライフラインへの影響、農作物・家畜への被害などが発生しました。
この台風19号による大雨・強風により さいたま市内では県内でもっとも多い871件の床上浸水と292件の床上浸水の住家被害が出ました。
なかでも さいたま市の南東部にある桜区では、床上浸水が さいたま市全体のおよそ8割となる689件、床下浸水が7割を超える210件、住宅の一部損壊は79件と全体のおよそ4割を占める甚大な住家被害に見舞われました。
しかし、台風19号による住家被害は 床上・床下浸水や住宅の一部損壊といった目に見える被害だけではなく、雨水の侵入による雨漏りなど目には見えない深刻な住家トラブルも引き起こしています。
ここでは、台風による雨漏り被害から大切な家族と住宅を守るため 台風に備えた雨漏り対策リフォームについてご説明します。
台風と雨漏りについて
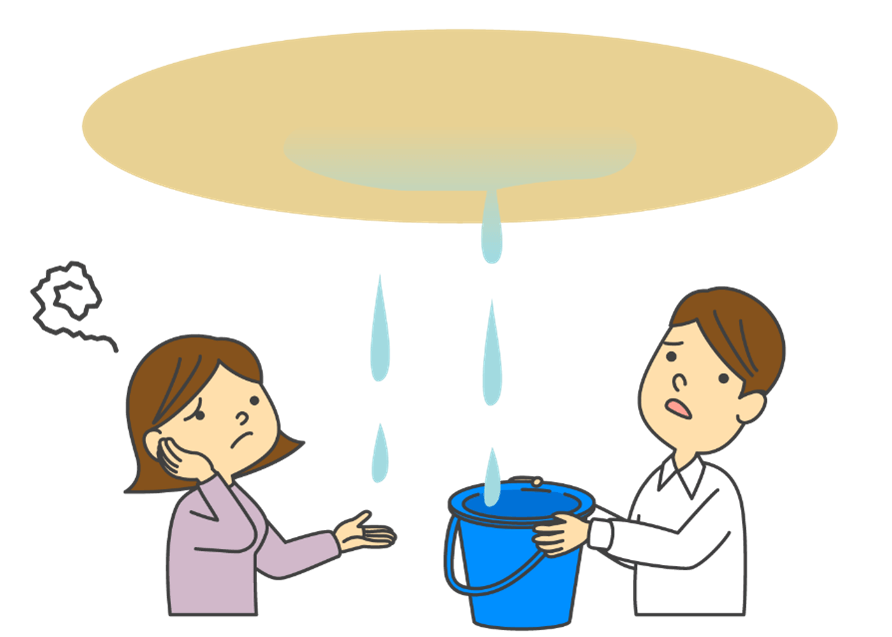
雨漏りとは、雨水が住宅内部へと侵入している状態です。
雨漏りの一般的なイメージは 主に「天井からポタポタと雨水が垂れてくる」ですが、ほかにも 天井・壁紙の剥がれ、コンセントボックスから発せられるカビ臭、窓サッシの雨染み・錆び、天井裏・壁内から聞こえる雨音なども雨漏りの発生時にみられる症状の一例になります。
雨漏りが発生しているのに 何の対策も取らず放っていると 構造躯体の劣化・シロアリの発生などによる住宅の強度・耐震性の低下、 カビ・ダニの発生による健康被害、高額な補修・修繕費用の発生などにつながり、安心・安全で快適な暮らしが脅かされる原因となります。
雨漏りは発生部分によって なかなか気が付かないことも多く、とくに台風19号のような非常に勢力の強い台風が上陸した場合には 屋根・外壁などの外装材が破損し 雨水が住宅内部に入り込みやすくなります。
また、住宅の構造によっては雨水が侵入しやすい部分もあり、なかでも 換気扇や通風口といった換気を行う設備は雨水が侵入しやすいため 台風の勢力によっては何かしらの対策を取る必要があります。
海洋研究開発機構によると 地球温暖化による海水温度の上昇により今後ますます台風の勢力が強まる可能性が高いとし、一部の専門家からは 日本を含む中緯度では こうした勢力の強い台風が接近・上陸するリスクが増大すると示しています。
台風への備えに 雨漏りしやすい部分をチェック
屋根
住宅のなかで もっとも過酷な自然環境にさらされている屋根は、ほかの建材や住宅設備と比べて 劣化・破損しやすいことから 雨漏りの主な発生源とされています。
しかし、屋根は 住宅のもっとも高い位置にあるため、経年による劣化や自然災害による破損・損壊が生じていたとしても 気が付きにくく、補修・修繕の対応が遅くなってしまい 高額な補修・修繕費用が発生することも少なくありません。
定期的に屋根材、棟板金・棟瓦、防水シートを点検・メンテナンスを実施し 屋根から侵入する雨水を防ぐことがポイントです。
外壁
屋根と共に紫外線や風雨などの厳しい自然環境から家族を守る役割を果たす外壁は、定期的に塗装工事を行うことで 雨水が住宅内部に侵入することを防ぐことができます。
しかし、外壁の塗装に使用されている塗料は経年によって少しずつ劣化し 防水機能も徐々に低下していきます。
外壁材は水に強い建材ではありませんので、塗料の防水機能が低下してしまうと 外壁材に雨水が通りやすくなります。
雨水を含んだ外壁材は次第にひび割れや雨染みなどの劣化・破損が生じ、よりたくさんの雨水が住宅内部に侵入しやすくなります。
また、紫外線などによって 外壁材同士の継ぎ目に使用されているコーキング剤 (シーリング材) が劣化してしまうと ひび割れや剥がれなどの症状が現れ、外壁材同士の継ぎ目部分から住宅内部へと雨水が侵入しやすくなり 室内壁を中心とする雨漏りを引き起こす原因となります。
太陽光発電・太陽熱温水器システム
省エネ・エコ志向が高まりつつあるさいたま市では、住宅の屋根に太陽光発電や太陽熱温水器の導入に欠かせないソーラーパネル、集熱器を設置される世帯が増えています。
しかし、ソーラーパネルや集熱器の設置に慣れていない事業者が設置工事を担当してしまうと 屋根材に開けられた穴の隙間から雨水が侵入し 雨漏りが生じるリスクが高くなります。
太陽光発電や太陽熱温水器を導入・設置する際は、屋根の構造に詳しい確かな施工技術を持つ事業者に設置の依頼を行うと良いでしょう。
なお、ソーラーパネルなど太陽光発電の導入に必要な機材の設置を行う場合は 万が一のことを想定し 太陽光発電に関する補償内容を併せて確認しておくと設置・導入後のトラブルを防ぐことができます。
ベランダ・バルコニー
住宅の屋外スペースとして 洗濯物を干したり、プランター菜園やガーデニングを楽しんだりと さまざまな目的や用途で利用されているベランダ・バルコニーですが、つねに紫外線や風雨にさらされており 人の出入りも多いため 劣化しやすく ダメージが蓄積しやすい場所になります。
そのため、定期的な点検・メンテナンスを怠ってしまうと 住宅内部に雨水が侵入しやすくなり 雨漏りを引き起こす原因となります。
また、2階・3階建て住宅やアパート・マンションでは ベランダ・バルコニーの劣化・破損によって下層階に雨漏り被害が生じることも多く、アパート・マンションにお住いのご家族は 下層階の住民と雨漏りトラブルに発展しないよう ベランダ・バルコニーの定期的な防水工事・排水ドレンのメンテナンスなどを実施するようにしましょう。
窓サッシ・換気扇・通気口などの換気設備
台風の上陸に伴う大雨・強風により窓サッシ・換気扇・通気口などの換気設備から住宅内部に雨水が侵入することがあります。
通常 換気設備を取り付ける際には 隙間から住宅内部に雨水が入り込まないようにサッシ部分にパッキンが施されています。
しかし、パッキンの寿命は10年~20年ほどであり 寿命を迎えた状態のパッキンをそのまま使い続けてしまうと 老朽化によって隙間が生じ 雨漏りの原因となります。
地震などの自然災害によって窓サッシに歪みやひび割れなどのトラブルが生じた場合 そこから雨水が住宅内部へと侵入し 壁紙の剥がれやコンセントボックスから発せられるカビ臭などの雨漏り被害につながります。
とくに採光などを目的に設置された天窓は一般的な窓サッシとは違い 非常に厳しい自然環境下にさらされることになりますので、台風・地震などの自然災害に備えて 日ごろから点検・メンテナンスを実施するようにしましょう。
台風の上陸に備えた雨漏り対策リフォーム

地球温暖化の影響により海水の温度が上昇することで 今後ますます勢力が強くなると予想されている台風に備え、少しでも住家被害を抑える対策リフォームを早めに実施する必要があります。
台風でもっとも注意しなければならないのは「強風」です。
日本では 北西太平洋または南シナ海にて発生した熱帯低気圧のうち 低気圧域内の最大風速が17m/s (34ノット、風力8) を超えるものを台風と定義しています。
2019年9月に関東地方に上陸した2つの台風 台風15号と台風19号は 中心付近の最大風速が40m/sと強かったため、看板は落下・飛散し 根がしっかりと張っていない樹木は倒れ、屋根材の飛散・飛来物による破損など 各地で多くの住家被害が発生しました。
勢力の強い台風から住宅を守るためにも 台風シーズンを迎える前に台風の上陸に備えた住宅リフォーム・リノベーションを実施することをおすすめします。
もっとも台風の影響を受けやすいのは屋根と窓
台風による住家被害の多くが強風によるものです。
なかでも 屋根と窓は強風の影響により 飛散・破損などの影響を大きく受けやすいため、築年数を問わず 定期的に屋根・窓の状態をチェックすることが大切です。
少しでも屋根・窓に異常を感じたら 台風シーズンを迎えたら 1度 信頼できる専門業者に屋根と窓の点検を行ってもらうと良いでしょう。
屋根のセルフチェック
天井や壁紙に雨染みができている。
屋根と雨どいの隙間から水がポタポタ垂れている。
軒天に雨染みができている。
屋根裏・天井裏に濡れて乾いた染みがある。
屋根材の金属部分が錆びている。
ひび割れ、剥がれ、浮き、ズレなどの劣化症状が見られる。
屋根材が部分的に変色している。
屋根の表面にコケ・藻が生えている。
庭先やベランダなどに屋根からの落下物がある。
雨どいなどの排水設備にゴミが溜まっている
窓のセルフチェック
外壁と窓枠の隙間を埋めるコーキング剤にひび割れ、剥がれなどの劣化が見られる。
外壁にひび割れ、色褪せ、コケ・藻の発生、塗膜の剥がれなどの劣化が見られる。
窓には水滴がついていないのにサッシが水で濡れている。
窓サッシ周辺の壁紙クロスに雨染み、変色、剥がれなどが見られる。
雨が降ると湿度が異常に高くなる。
室内がカビ臭い。
窓サッシ周辺の床材が濡れて 水たまりができている。
窓サッシ周辺の床材にカビが発生している。
屋根の主な雨漏り対策リフォーム
屋根に何かしらの劣化・欠損が見られる場合、台風による住宅の損壊や雨漏り被害を防ぐため 屋根の補修工事を実施しましょう。
比較的軽度の劣化・欠損であれば、
- コーキングによる補修
- 棟板金の交換
- 谷樋の交換・撤去
- 屋根材の修理・交換
といった部分的な補修で対処することができます。
しかし、中度~重度の劣化・欠損が見られる場合 部分的な補修では住宅が台風に耐えることができない可能性があります。
その場合は 屋根全体をリフォーム・リノベーションする大規模な補修工事を行う必要があります。
屋根全体をリフォーム・リノベーションする大規模な補修工事には、既存の屋根に新しい屋根を取り付ける重ね葺き、既存の屋根を撤去して新しい屋根と交換する葺き替え、経年により衰えてしまった屋根の防水機能を回復させる屋根塗装があります。
台風対策にもっとも有効的とされている補修工事は 葺き替えになりますが、既存屋根の状態によって適切な補修工事が異なりますので、1度 屋根専門のリフォーム業者に既存屋根の状態を確認してもらうことをおすすめします。
窓サッシ周辺の主な雨漏り対策リフォーム
窓サッシ周辺に劣化・欠損が見られる場合、住宅内部に雨水が侵入しやすくなります。
台風シーズンを迎える前に窓サッシ周辺の雨漏り対策を実施しましょう。
経年による劣化が原因で 外壁と窓枠の隙間に埋めたコーキングに ひび割れ、しわ、剥がれ、肉やせ、べたつき、柔らかくなる といった症状が現れた場合、コーキングの打ち替えまたは増し打ちによる補修工事が行われます。
窓サッシ周辺からの雨漏り対策としてコーキングの補修工事を実施するのであれば、劣化した古いコーキング剤を取り除き新しいコーキング剤を充填する打ち替えによる補修を行うと良いでしょう。
天窓のある住宅では、外側の屋根と天窓の隙間に風で飛ばされてきた土砂や枯葉などのゴミが原因で雨漏りを引き起こしている可能性があります。
定期的に天窓を掃除してゴミが溜まらないよう注意しましょう。
なお、耐用年数を超えた天窓を使い続けていると 雨漏りだけではなく屋根にも悪影響を及ぼす原因となります。
天窓の耐用年数は20年~25年ほどになりますが、紫外線や風雨などの影響により 実際にはもっと早い段階で寿命を迎えることになります。
天窓のある住宅では 定期的かつ早めの台風対策を実施するようにしましょう。
台風による住家トライブルが発生した場合の応急処置
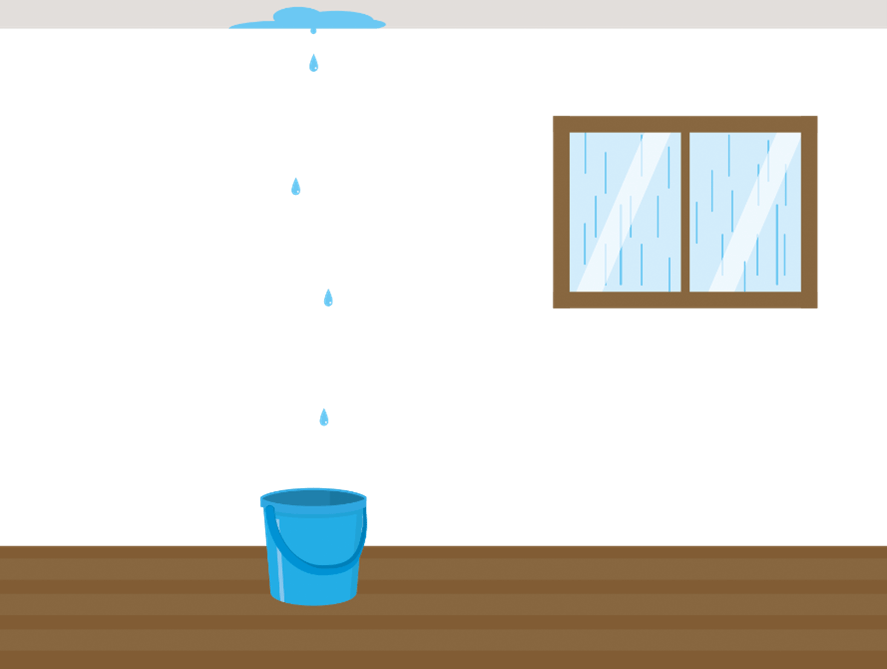
万が一 台風による住宅の一部損壊や雨漏りなどの住家被害が発生した場合、自宅にあるものを使って住宅の応急処置を行いましょう。
河川の氾濫による床上浸水への対策には ホームセンターなどで購入できる土のうを堤防のように積み上げることで 玄関などの開口部から住宅内に水が入り込むことを防ぐことができます。
土のうの用意が間に合わなかった場合、家庭用ごみ袋に半分程度の水を入れ ゴミ袋のなかにある空気をしっかり抜いてくちを結んだ「水のう」を手づくりし ダンボール箱に入れて玄関などの開口部に設置しましょう。
水のうは 浴室・トイレなどの排水口からの逆流も防ぐことができますので、作り方を覚えておくと たいへん便利です。
天井からポタポタと雨漏りしている場合、雨漏り箇所が少なければ バケツなど水を溜められるものを置いて対処することができますが 雨漏り箇所が多い または 大量の雨水が住宅内に侵入している場合は 吸水シートを使って雨水を吸い取るのがおすすめです。
壁紙・窓サッシ周辺で雨漏りが発生した場合には、カーテンが雨水を吸い込んでカビが発生しないよう 速やかにカーテンを取り外してください。
台風による強風や飛来物により窓ガラスが破損してしまった場合、窓枠にピッタリと収まるサイズに切ったダンボールを養生テープもしくは布製ガムテープでしっかりと窓枠に取り付けてください。
紙製のガムテープでダンボールを固定してしまうと剥がす際にガムテープの跡が残ってしまうおそれがあります。
勢力の強い台風が上陸する前に雨漏り対策を行いましょう。

雨漏りが発生していることに気付いたときには大規模な修理・修繕が必要である場合も少なくありません。
埼玉県では2019年10月に関東地方に上陸した令和元年東日本台風 (台風19号) により、さいたま市をはじめとする多くの市町村で甚大な人的・住家被害が発生しました。
四季彩ホームでは、台風19号による屋根材の剥がれ、棟板金の外れ・浮きといった住家被害の補修・修繕をご依頼いただいたご家族を対象に 火災保険および被災した家屋の応急的な修理に要する費用支援などの申請サポートを実施させていただきました。
なお、火災保険の申請による保険金の請求期限は 原則3年以内となっており、2019年の3年後となる2021年は火災保険の保険金 請求期限の時効となります。
台風19号の上陸以降、雨が降るたびに雨漏りが発生しており お困りのご家族は 損害保険登録鑑定人が在籍している四季彩ホームまでご相談ください。