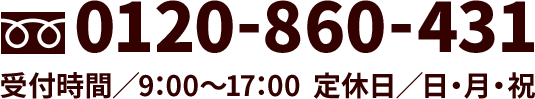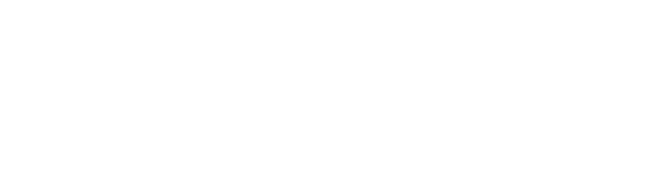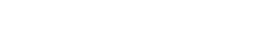住宅の豆知識
高額なリフォーム費用をお得に!リフォーム減税の確定申告や手続きの方法をご紹介
- 住宅の豆知識

ここ数年、日本全国で戸建て・集合住宅問わずリフォームへの潜在需要が高まっています。
とくにさいたま市では、30歳代から50歳代までの子育て世帯や共働き世帯を中心に具体的なリフォーム志向が強まっており、バリアフリー住宅や耐震性能など将来を見据えた住宅リフォームに注目が集まっています。
しかしリフォームを実施するとなるとどうしても高額な費用がかかってしまい、リフォーム工事を依頼したくても、予算の都合や家計の事情でなかなかリフォームに踏み切ることができないご家族も少なくありません。
そこで、さいたま市ではリフォーム資金の低利融資、住宅性能の向上に伴う改築・改修工事費用の補助、要介護者などを対象とする住宅改修費用支給等による補助・助成によるリフォーム支援に加え、リフォーム減税による所得税や固定資産税の減額も併せて行っております。
ところが、実際にリフォーム工事を行ったさいたま市民の多くが、リフォーム減税制度の条件を満たしているにも関わらず、うまく利用できていないのが現状です。
そこで今回は、あまり知られていないリフォーム減税制度とは何か、高額なリフォーム費用をお得にする確定申告や手続きの方法をご紹介します。
知っているとお得なリフォーム減税制度とは?

リフォーム減税制度とは、リフォーム工事を行う要件、施工内容と範囲、採用する住宅設備など国土交通省が定める一定の条件を満たすことで利用できる税金の減額等における優遇措置です。
減税対象となる主なリフォーム工事は、
- 耐震リフォーム
- バリアフリーリフォーム
- 省エネリフォーム
- 三世代同居対応リフォーム
- 長期優良住宅化リフォーム
この5つになります。
いずれのリフォーム工事も一定の要件を満たすことで税金の減額等を受けることが可能であり、また減税制度の対象となっているリフォーム工事を2つ以上組み合わせたリフォーム工事を実施した場合には、組み合わせによってリフォーム減税を併用して受けることが可能となっています。
リフォーム減税の種類
リフォーム減税制度の優遇措置が受けられる主な税金の種類は、
- 所得税の控除
- 固定資産税の減額
- 贈与税の非課税措置
- 登録免許税の特例措置
- 不動産取得税の軽減措置
この5種類になります。
さいたま市にて一定の条件を満たしたリフォーム工事を行った場合、減税対象となるのは基本的に「所得税の控除」と「固定資産税の減額」となります。
ただし、「贈与税の非課税措置」等が発生しそうな場合は、条件を満たすことができれば減税制度を受けることができるケースもあります。
なお、今回はリフォーム減税制度のなかでもっとも利用者の多い「所得税の控除」と「固定資産税の減額」この2つを中心にご説明させていただきます。
所得税の控除
国土交通省が定める一定の要件を満たした住宅リフォーム工事を行った場合に限り、税務署での確定申告時に必要な手続きを行うことで所得税の控除を受けることができます。
リフォーム減税制度による所得税の控除には、「投資型減税」「ローン型減税」「住宅ローン型減税」の3種類あり、それぞれの減税制度の種類に応じて控除期間や最大控除額などに違いがあります。
投資型減税 (住宅特定改修特別税額控除)
| 概要 | 控除の内容 |
|---|---|
| ローンの要件 | ローン利用の有無にかかわらず誰でも利用することが可能 |
| 所得税の控除率 | リフォーム工事の内容や種類問わず、標準的な工事費用相当額10% |
| 控除期間 | 1年 (リフォーム工事が完了した日の属する年分) |
| 最大控除額 | 耐震・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化: 25万円 / 35万円※1 / 50万円※2 バリアフリー:20万円 |
| 控除額 | ①・②いずれか少ない金額×10% ① 国土交通省が定めるリフォームの種類別 標準的な工事費用相当額-補助金等 ② 控除対象限度額 |
※1:省エネリフォームと合わせて太陽光発電設備設置工事を行った場合
※2:耐震および省エネリフォームと合わせて長期優良住宅化リフォームを行った場合
ローン型減税 (特定増改築等住宅借入金等特別控除)
| 概要 | 控除の内容 |
|---|---|
| ローンの要件 | 償還期間5年以上のリフォームローンを組んだ場合のみ利用可能 |
| 所得税の控除率 | 住宅性能向上リフォーム※費用の控除対象限度額2% および年末ローン残高の1% |
| 控除期間 | リフォーム後、居住を開始した年度から5年間 |
| 最大控除額 | 62.5万円 (12.5万円 / 年×5年間) |
| 1年間の控除額 | [㋑:①・②いずれか少ない金額×2%] ① 対象となるリフォーム工事費用-補助金等 ② 控除対象限度額250万円 +[㋺:㋑以外のリフォーム工事費用相当分の年末ローン残高×1%] |
※住宅性能向上リフォームとは、バリアフリー・省エネ・三世代同居対応・長期優良住宅化のこと。
住宅ローン型減税 (住宅借入金等特別控除)
| 概要 | 控除の内容 |
|---|---|
| ローンの要件 | 償還期間10年以上のリフォームローンを組んだ場合のみ利用可能 |
| 所得税の控除率 | リフォーム工事費用相当年末ローン残高の1% |
| 控除期間 | 10年間※ |
| 最大控除額 | 400万円 (40万円 / 年×10年間) |
| 1年間の控除額 | (リフォーム工事費用相当分の年末ローン残高-補助金等)×1% |
※消費税増税に伴い、2019年10月1日~2020年12月31日までに居住を開始した場合に限り、
控除期間を13年間に延長する拡充措置が適用される。
固定資産税の減額
リフォーム減税制度の適用条件を満たすリフォーム工事を行った場合、リフォーム工事完了後3か月以内に該当する住宅のある地域を管轄する市税事務所資産課税課にて申告手続きを行うことで固定資産税の減額を工事完了年の翌年1年度分受けることができます。
ただし、固定資産税の減額対象となるリフォームは、耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化のみであり、それ以外のリフォーム工事は対象外となります。
| リフォームの種類 | 軽減額 | 備考 |
|---|---|---|
| 耐震 | 固定資産税額の1/2 | 家屋面積120㎡相当分まで |
| バリアフリー | 固定資産税額の1/3 | 家屋面積100㎡相当分まで |
| 省エネ | 固定資産税額の1/3 | 家屋面積120㎡相当分まで |
| 長期優良住宅化 | 固定資産税額の2/3 | 家屋面積120㎡相当分まで |
固定資産税の減額は、リフォーム減税制度の対象となるリフォーム工事にかかる費用が補助金等を除き50万円(税込)以上であれば適用となります。
ただし、リフォームの種類ごとに対象となる工事内容や主な要件等が異なりますので、現在リフォームをご検討中のご家族のうち、希望するリフォーム案が固定資産税の減額対象となるかどうか気になる際は、四季彩ホームまでご相談ください。
知っているとお得な減税制度「贈与税の非課税措置」とは?
リフォーム減税制度では、基本的に「所得税の控除」と「固定資産税の減額」この2つがメインとなっています。
しかし、もうひとつ知っているとお得なリフォーム減税制度があります。それは、「贈与税の非課税措置」です。
満20歳以上の個人がリフォーム工事を行う際、両親や祖父母などから住宅取得等にかかる費用を援助してもらった場合、本来ならば贈与税を支払わなければなりません。
ところが、直系尊属にあたる両親・子ども・祖父母からの費用援助であれば非課税の対象となる場合があります。
ただし、義父母から子どもへの費用援助は非課税の対象となりますが、叔父・叔母、配偶者の父母や祖父母からの費用援助は、直系尊属からの贈与に当てはまらないため課税対象となります。
なお、リフォーム減税制度に含まれる「贈与税の非課税措置」は、対象となる工事内容、主な要件、適用期限等がきっちりと定められております。贈与税の非課税措置に関するご相談は国税庁または管轄区域の税務署にお問い合わせください。
リフォーム減税制度の申告手続きの流れ

リフォーム減税制度の申告手続きは、利用したい減税制度によって必要となる各種証明書や申請書類が違います。
また、リフォーム減税制度の対象となる期間や申告先も違いますので、リフォーム工事を依頼する前にどのような減税制度を受けることができるのかリフォーム業者としっかり話し合うことが大切です。
減税制度を利用するための手順
①見積書の確認とリフォーム資金計画書の作成
・最終的な見積金額をきちんと確認後、リフォーム資金計画を立てます。
②利用したいリフォーム減税制度の条件確認
・減税制度の各要件をクリアしているかを含め、リフォーム工事の内容やスケジュールなどを細かく確認しましょう。
・どのような減税制度が利用できるのかも併せて確認しておくと安心です。
③申請手続きに必要となる証明書や書類の確認
・リフォーム減税制度を申請するための証明書や書類の手続き方法と提出期限を確認します。
④申請時に必要な契約書類と内容の確認
・工事請負契約書と領収書の写しを確認後、申請時まで無くさないよう大切に保管しておきましょう。
⑤申請時に欠かせない各種証明書の作成を依頼
・リフォーム減税制度の申請手続きを行う場合、
- 建築士事務所登録済みの建築士事務所に所属している建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
- 地方公共団体 (耐震リフォーム限定)
いずれかの担当者に申告手続きに必要な証明書を発行してもらいましょう。
⑥必要な各種証明書と書類を揃えて申告先に提出
・期日までに必要な証明書と書類を揃えて税務署または各市区町村に提出しましょう。
リフォーム減税制度の各種申告時の手続き方法
所得税の控除
- 耐震リフォームの場合
増改築工事証明書と住宅耐震改修証明書を入居日の翌年の確定申告期間中に住宅のある地域を管轄するさいたま市の税務署に提出する。
- バリアフリー、省エネ、三世代同居対応、長期優良住宅化、住宅ローン減税の場合
増改築工事証明書を入居日の翌年の確定申告期間中に住宅のある地域を管轄するさいたま市の税務署に提出する。
固定資産税の減額
- 耐震リフォームの場合
増改築工事証明書と住宅耐震改修証明書をリフォーム工事完了後3ヶ月以内に埼玉県もしくはさいたま市に提出する。
- バリアフリーリフォームの場合
物件所在のある埼玉県またはさいたま市にお問い合わせください。
- 省エネ、長期優良住宅化リフォームの場合
増改築等工事証明書をリフォーム工事完了後3ヶ月以内に埼玉県もしくはさいたま市に提出する。
贈与税の非課税措置
増改築等工事証明書 (住宅取得資金の贈与の特例用)を、贈与を受けた年度の翌年の確定申告期間に住宅のある地域を管轄するさいたま市の税務署に提出する。
※所得税、登録免許税および不動産取得税とは書式が異なる点にご注意ください。
リフォーム減税制度で必ず必要となる「増改築工事証明書」とは?

リフォーム減税制度を利用する場合、必ず「増改築工事証明書」の提出が求められます。
増改築工事証明書とは、リフォーム工事を行ったことを証明するための書類であり、所得税の控除や固定資産税の減額、贈与税の非課税措置など減税制度を利用する際に欠かせないものです。
増改築工事証明書の取得は、
- 建築士事務所登録が済んでいる建築士
- 指定の確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅化被担保責任保険法人
など、専門知識を持ったいずれかの人でないと発行することができません。
そのため、依頼したリフォーム業者さんに該当する人物がおらず、増改築工事証明書の発行が難しい場合は、増改築工事証明書を発行できる人に代行依頼をする必要があります。
増改築工事証明書の発行に必要なものリスト
- リフォーム工事を行った住宅の登記事項証明書
- 工事請負契約書
※リフォーム業者と交わした工事請負契約書またはその写しが手元にない場合、
リフォーム工事の費用に関する領収書、リフォーム工事代金の支払いが確認できる振込みの控え、通帳のコピーなど、リフォーム工事の前後を撮影している場合、それぞれの状況を示した該当写真でも問題ありません
- 設計図書、そのほか設計に関する書類等
※書類等が手元にない場合、工事を行う前と行った後が確認できる間取り図面または写真でも可能。
※省エネリフォーム工事を行った場合、リフォーム箇所について新たに現行の省エネ基準以上の省エネ性能となるリフォーム工事を行ったことが確認できる書類等が必要となります。
- リフォーム費用の総額が30万円以上であることが確認できる工事費内訳書または領収書等
※リフォーム減税制度の対象となるリフォーム工事をいくつか組み合わせて行った場合、各リフォーム工事に共通する経費については、それぞれのリフォーム工事に要した費用の割合に応じて振り分けた金額を算入すること。
- そのほかの補助金等の交付または給付を既に受けている場合、それらを証明する書類等
- 住民票の写し
※増改築工事証明書を発行する場合、
施主様本人が所有し居住している住宅であること、リフォーム工事が完了した日より6か月以内に居住すること、リフォーム工事後の住宅床面積が50㎡以上かつその1/2以上が施主様ご家族の居住区であることの3つの条件を全て満たしている必要があるため住民票の写しが必須となります。
増改築工事証明書が必要な場合、基本的には上記の書類等があれば問題なく発行できます。
しかし、発行を依頼する業者によって必要な証明書や書類等が異なります。
リフォーム減税制度の利用を視野にリフォーム工事をご検討中のご家族は、増改築工事証明書を発行するのに何が必要なのかを事前に確認しておくことをおすすめします。
増改築工事証明書の発行費用について
増改築工事証明書の発行を依頼する際、業者によって発行費用を求められるケースがあります。
増改築工事証明書の発行費用については、発行する側によってバラつきがあるため一概には言えませんが、リフォーム工事を依頼した業者に増改築工事証明書を発行できる人がいる場合は1部あたり無料~1万円ほどが相場となっています。
一方、リフォーム工事を依頼した業者に増改築工事証明書を発行できる人がいない場合、発行できる第三者に依頼する必要があるため1部あたり5万円前後かかってしまうケースもあります。
また、増改築工事証明書の発行時、リフォーム工事を行う前と行った後の間取り図面またはリフォーム工事を行ったことがはっきりと分かる工事前後の写真が用意できない場合、現地調査が必要になることがあります。
現地調査にかかる費用は基本的に「交通費のみ」の場合が多いのですが、業者によっては交通費とは別に「現地調査費」が発生することがあります。
現地調査が必要な際は、事前に調査費用について業者に確認しておくと良いでしょう。
さいたま市の各種制度をうまく利用してお得にリフォーム工事をしましょう。

30歳代から50歳代までの子育て世帯や共働き世帯を中心にリフォーム潜在需要が高まっているさいたま市ですが、予算の都合や家計の事情でリフォーム工事をしたくても、なかなか踏ん切りがつかずお困りのご家族も少なくありません。
さいたま市では、さいたま市民が安心・安全に暮らせる住み心地の良いまちづくりの一環としてリフォーム資金の低利融資や住宅性能向上に伴うリフォーム費用の補助や助成制度を用意しています。
四季彩ホームでは、バリアフリーリフォームを中心とする所得税の控除や固定資産税の減額などに関するリフォーム減税制度とさいたま市が推進するリフォーム費用の補助・助成制度をうまく利用するためのリフォーム工事のお悩みやご質問を承っています。
ぜひお気軽にご相談ください。